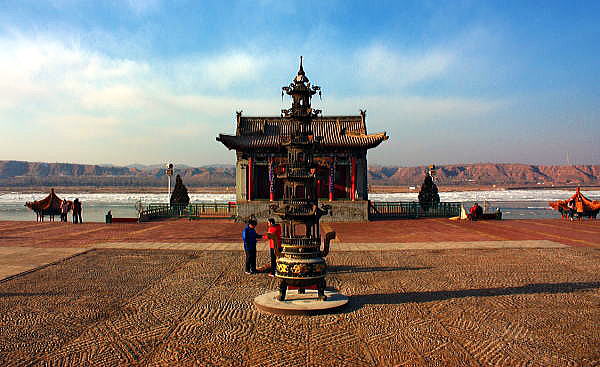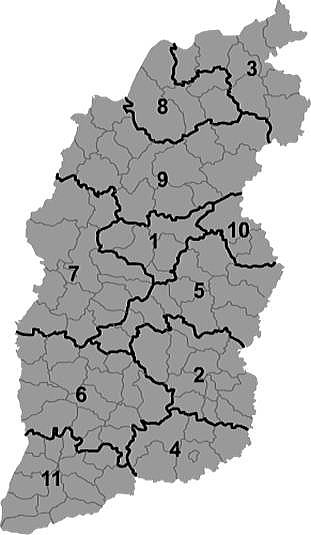�@�{�_�l�͈ȉ��̎����A���A�ʐ^�Ȃǂ����ƂɎ��M���Ă��܂��B
�@�P�D�����F�D�L�O�u�_�}�ځv�œ��肵�������A
�@�@�@�u�s��ȗ��j�Ƃ̏o��@�R���ȁ@��ʌ��R���ȗF�D�L�O�فv�A
�@�Q�D�����F�D�L�O�u�_�}�ځv�ŎB�e�����ʐ^�A
�@�R�D�������Ɗό��ǎ����A
�@�S�D�R���ȖȎR���i�������A
�@�T. �R���ό��ǃz�[���y�[�W
�@�U. �ۊ�S�ȁC���R�I�S�ȑS(Wikipedia)�A
�@�V. ���{��A������A�p���Wikipedia�A
�@8. �O�[�O���}�b�v�A �O�[�O���A�[�X�@
�@�Ȃ��A�R���Ȃɂ͈ȉ��̐��E��Y������܂�
�@�E�����̒���i���̂��傤���傤�j
�@�E�ܑ�R�i����������j
�@�E�_���ΌA�i�����������j
�@�E���y�Ï��i�ւ��悤�����傤�j
�@
���R���Ȃ̈ʒu

�����ɂ�����R���Ȃ̈ʒu�@�@�o�T�FWikipedia
���R���ȍs���敪�}
�@�R���Ȃ͂P�P�̎s����\������Ă��܂��B�Ȃ��A�ȓs�͂P�̑����s�ł��B
�@�Ȃ��A�{�_�l�ł́A�P�P�̎s�̂����A�����s�A�哯�s�A�W���s�A�՟��s�A�^��s�ɂ��閼�鋌�ՁA���@�A�������Ȃǂ��Љ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
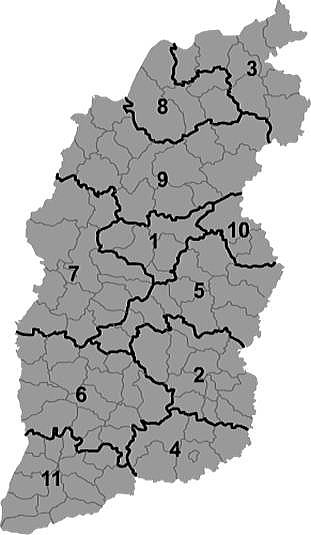 |
| �� |
���� |
�@�ʐ� |
�l�� |
|
|
(K�u) |
2010 |
| 1 |
�����s�@�@ |
6909.96 |
�@�@4,201,591 |
| 2 |
�����s |
�@�@13957.84 |
3,334,564 |
| 3 |
�哯�s |
14102.01 |
3,318,057 |
| 4 |
�W��s |
9420.43 |
2,279,151 |
| 5 |
�W���s |
16386.34 |
3,249,425 |
| 6 |
�՟��s |
20589.11 |
4,316,612 |
| 7 |
�C���s |
21143.71 |
3,727,057 |
| 8 |
��B�s |
10624.35 |
1,714,857 |
| 9 |
�v�B�s |
25150.69 |
3,067,501 |
| 10 |
�z��s |
4569.91 |
1,368,502 |
| 11 |
�^��s |
14106.66 |
5,134,794 |
|
�o�T�FWikipedia����쐬
�@�ȉ��͎R���Ȃ̏ȓs�A�����s�̎ʐ^�ł��B

�ȓs�����s�@�o�T�F�R���ό��ǃz�[���y�[�W

The Shanxi Museum located on the west bank of Fen River in downtown Taiyuan
�R�������@�@�@�o�T�FChinese Wikipedia

�哯�s�̉_���ΌA�@�@�@�o�T�FWikipedia
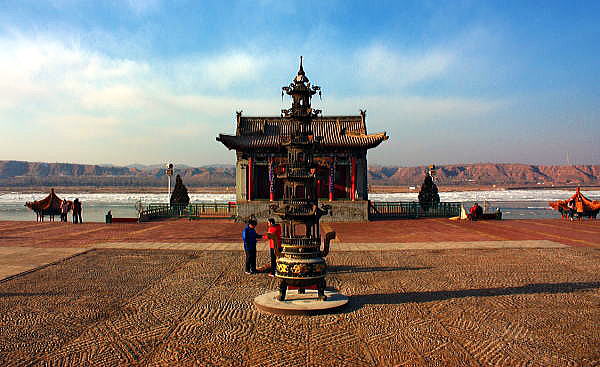
Western gate of a Temple of Heshen (River God) in Hequ, Xinzhou.
�R�������@�@�@�o�T�FChinese Wikipedia

Temple of Guandi in Datong.
�o�T�FChinese Wikipedia
�������R���Ȃ̊T�v
�@�܂��͒����R���ȊT�v�̂����炢����͂��߂܂��傤�B�o�T��Wikipedia�ł��B
 |
�@ |
�@�R���ȁi�p��:Shanxi�j�́A���ؐl�����a���̍s���敪�̈�B�ȓs�͑����s�B���̂��W�ł��B
�n��
�@�k�͖����̒��������œ������S��������ƁA���͑��s�R��������ʼn͖k�ȂƁA��͉��͂�����ʼn͓�ȂƁA���͖k�サ�����͂������蟐��ȂƂ��ꂼ��ڂ��Ă��܂��B
�@�R�������͉��y�����̓����ɓ�����A�k���ł͊C�͐��n�̟��͂�K���͂����֗���A��������암�͉��͐��n�̟��͂��т��Ă��܂��B��v�s�s�͑����ȊO�ɂ͑哯������܂��B
����
�@�\�������͊����A�A�����S�����A���B���ȂǁB������̂����W��i�W�����j���b����Ă��܂��B
���j
�@�t�H����ɂ��W�̗̈�ł���A�W�����͑啔������A�ꕔ���؋y��鰂ɑ����܂����B�`��ȍ~�����S�A�͓��S���̊NJ��Ƃ���Ă��܂��B
�@���W�̎���ɂȂ�ƛ�B�A�i�B�A�H�B���ݒu����A�܌ӏ\�Z������̑O��E����E�k鰂���������哯�����s�ƒ�߂܂����B��k������ɂȂ�Ɩk鰂ɂ���B�E���B�E�P�B�E��B�E���B�E�W�B�E�B�E��贏B��8�B���A�@��ɂ͑����A��}�Ȃǂ�13�S���ݒu����܂����B
|
�@�@���ɂȂ�Ɨ������R���ȂŋN�������������ĎR���n��͉͓����Ə̂���܂����B�v��ɂ͉͓��H�Ƃ���܂������A�哯���ӂ͉��_�\�Z�B�̈ꕔ�Ƃ��ėɒ��̎x�z�n��ƂȂ�܂����B
�@����ɂȂ�ƎR���n��͒����Ȓ����Ƃ���R������Ԏi���ݒu����A����ȍ~����ł�1369�N�i�^��2�N�j�ɎR���s�����ȁi1348�N�ɎR���z���g�i�Ɖ��́j�A����ł͎R���ȂƁu�R���v�̖��̂��g�p����܂��B
�@���ؖ�����������R���Ȃ��ݒu����܂������A1914�N�i����3�N�j�ɏȖk���Ɏ@�������ʋ��i��̎@�����ȁj���ݒu����A1952�N�܂ŎR���Ȃ���ʍs�����Ƃ���Ă��܂����B
�o��
�@���C���ɔ�ׂ�ƁA���Ȃ�n�����n��ł����A�哯�⑾���ɂ͑�^�̒Y�z������܂��B�����o�ώj��A�R�����l�i�W���j�͑S���ɐ��͂������A�����̋��Z���x�z���Ă��܂����B�ߔN�ł͌o�ϔ��B�ɔ����A�R�����{�����ݑ�s�s���̕s���Y������ϋɓI�ɍs���Ă���Ƃ����Ă��܂��B
�E���R�����F�ΒY�A�S�@�[�@�哯�A�����ɂ͒Y�B������
�E�H�ƁF�S�|�A�d�@�A�����ԁA���w�H��
�E�_�ƁF���A�g�E�����R�V�A����i�����R�V�j�A�`�A�����Ȃ�
�E�ό��F���E��Y�@�[�@�_���ΌA�i�哯�j�A���y�Ï�Ȃ�
�R�����l
�@�����̎R���ȏo�g�̏��l�E���Z�Ǝ҂̑��̂ł��B�R���͌Â�����S�̎Y�n�Ƃ��Ēm���A�ܑ�ȍ~���l�̐��͂��`������͂��߂܂������A�ł������͖̂�������ł��B
�@����ɂ͖k�Ӗh�q�̗��M���m�ۂ��邽�ߊJ���@���{�s���܂������A�n�̗��Ă����R�����l�͕č����Ɖ��������˂ċ����Ă��܂����B����ɂ��̎��������Ƃɋ��Z�Ƃɂ��i�o���A�����͈͂�S���Ɋg���A�V�����l�ƂƂ��Ɍo�ϊE���x�z���܂����B����ɂ͉�����T�^�Ƃ��鐭���Ƃ��ė��v�Ă��܂������A����ɂ͕[���i�בցj�E�K�܁i���ցj�E�F�[�i�ݕ��K���j�E���s�i�����j�̌o�c�ȂNj��Z�Ƃ���Ƃ��A���̕x�Ŋ��E�ɉe���͂������A�y�n�ɑ��Ă��ϋɓI�ɓ������Ă��܂����B
�@�R�����l�͓k�퐧�x��ʂ��ē��������Ŏ炵�A�g���g�D���łߍ��J�����������ɂ��āA�e�n���R����������ĂĊ����̍����n�Ƃ��Ă��܂����B19���I�㔼�ɂ͑S���̈בƖ����قƂ�ǓƐ肷��قǂł������A�V����s�̔��B�⍑�یo�ς̒����Z���ƂƂ��ɐ��ނ��Ă䂫�܂����B
�@�O���u�ɏo�Ă��铯�����։H��M���n�߂��̂͂��̎R�����l�ł���A���݂ł͒����S�y�͂��납�A�؋��̂��鐢�E�e�n�ɁA�֒�_���Ղ���悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�o�T�FWikipedia
���R�����l�i�������傤�ɂ�j
Shan-xi shang-ren; Shan-hsi shang-jen
�@�����̖��E������Ɋ����R���ȏo�g�̏��l���w���܂��B�ނ�̖u���͖��̕Ӌ�����C�J���@�̎��{�Ɩ��ڂȊW������C�����S���l�Ƃ̐킢�Œ����тɒ��Ԃ������̏���R�ɑ��鏔�����̋��������ċ��������߁C�n�̗��ď��ƊE�Ɋ��܂����B
�o�T�F�R�g�o���N |
�@
�� |