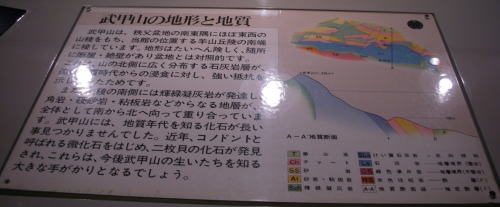●武甲山
秩父市の市域のほとんどが秩父多摩甲斐国立公園や、武甲・西秩父といった埼玉県立の自然公園に指定されている。荒川が南西から北東に流れ河岸段丘を形成する。市の南東にそびえる武甲山では石灰石を産出し、露天掘りが行われている。
下はグーグルマップの地形図でみた秩父市である。秩父市は周りを1000m級の山々に囲まれた盆地である。その秩父市内からよく見える武甲山は、市の南にある。

グーグルマップの地形図でも秩父市
上述したように、秩父と言えば武甲山だ。秩父ではどこからでもこの武甲山がよく見える。
 撮影:青山貞一 Nikon Digital Camera Cool Pix S8
撮影:青山貞一 Nikon Digital Camera Cool Pix S8
秩父事件を描いた「草の乱」にも武甲山の映像がでてくる!

「草の乱」より
武甲山は、秩父盆地の南端にある山で、現在の標高は1,304mである。
秩父市と横瀬町にまたがって位置し別名を秩父嶽、妙見山、武光山などとも言われ奥武蔵・秩父の山の盟主とされている。
また先に紹介した秩父地方の総社である秩父神社の神奈備山とされる。日本二百名山の一つにも数えられる。
「武甲山」の名称は、日本武尊が東征の際、自らの甲をこの山の岩室に奉納したという伝説に由来すると一般にいわれている。
かつての武甲山は秩父盆地の南側に急峻で男性的な山容をもって威圧的に聳えており、日本武尊は、この山の姿を見て「勇者の肩を怒らせるが如し」と評したともいわれるが、現在ではセメント原料の石灰岩の採掘のため、怒った肩はすっかりこそげ落ち、秩父盆地から見る姿は以前に比べ貧相なものとなっている。
それでも武甲山は奥武蔵の最高峰であることには変わりない。

撮影:青山貞一 Nikon Digital Camera Cool Pix S8
武甲山の石灰岩は日本屈指の良質な大鉱床であるという。
可採鉱量は約4億トンと推定され、山の北側斜面が石灰岩質であるために古くから漆喰などの原料として採掘されていた。
明治期よりセメントの原料として採掘が進められ1940年(昭和15年)に秩父石灰工業が操業を開始して以降、山姿が変貌するほど大規模な採掘が進められている。
とくに北斜面で山体の崩壊が著しい。実際、北斜面では痛々しい程の露天掘りの後が見える。
※秩父石灰工業株式会社
自然植生から見ると、武甲山は石灰岩質の特有の山野草が豊富である。石灰岩採掘により、北側斜面は植生がほとんど見られない。
秩父盆地方面から見ると白っぽく見えるが、他方向の斜面は以前として自然豊かな森林となっている。チチブイワザクラは埼玉県希少動植物種となっている。また伏流水は平成の名水百選に選定されている。
下は武甲山資料館の入り口である。

撮影:青山貞一 Nikon Digital Camera Cool Pix S8
資料館で武甲山の歴史についてのDVDを見た。それによると下の図にあるように、武甲山はすでにもともとの標高から比べると、石灰石の採掘で30数m低くなっているが、今後さらに北側斜面は採掘で順次低くなっていくとされている。
いくら良質の石灰石が採掘できるとは言え、このような由緒ある山の地形を人為的に改変してよいものだろうか? と思った。

撮影:青山貞一 Nikon Digital Camera Cool Pix S8
武甲山の標高だが、1900年(明治33年)の測量では標高は1,336メートルを記録したが、山頂付近も採掘が進められたために三角点が移転させられ、1977年(昭和52年)には標高1,295メートルとされた。
2002年に改めて三角点周辺を調査したところ、三角点より西へ約25m離れた地点で標高1,304mが得られ、国土地理院はこれを武甲山の最高地点と改めた(国土地理院の発表日時:2002年11月8日(金)14時00分)。そして、地図上では1,295mの三角点と最高地点1,304mの両方を表示することとした。
以下は資料館にあった武甲山の地形と地質についての解説。
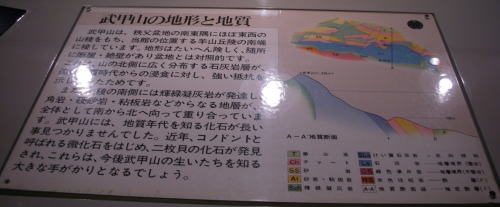
撮影:青山貞一 Nikon Digital Camera Cool Pix S8
下はかつての武甲山の勇姿である。

撮影:青山貞一 Nikon Digital Camera Cool Pix S8
下は昭和20年代の武甲山の勇姿。

撮影:青山貞一 Nikon Digital Camera Cool Pix S8
下は武甲山で採取された蝶類である。結構希少種もあった。

撮影:青山貞一 Nikon Digital Camera Cool Pix S8
下は国家にも読まれている「さざれ石」(=石灰石)。

撮影:青山貞一 Nikon Digital Camera Cool Pix S8
本ブログ各項目の参考文献:Wikipedia
つづく
|