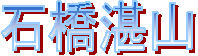Copy Right and Credit 佐藤清文著 石橋湛山
初出:独立系メディア E-wave Tokyo、2007年10月16日 本連載の著作者人格権及び著作権(財産権)は すべて執筆者である佐藤清文氏にあります。 リンク以外の無断転載、無断転用などをすべて禁止します。 |
|
第三節 新農業政策論 湛山が経済ジャーナリストに転身してから最初に手がけたのは、実は、農業問題である。明治を通じて米価は市場によって決定され、非常に不安定な状態が続いている。前年の大暴落を受け、1915年(大正4年)、政府は米価調整令を公布し、さらに1921年(大正10年)米穀法と米穀需給調節特別会計法を設け、米の買い入れを行っている。これはいずれも米価の低落を防止し、農家を経済救済する目的で実施されている。湛山は、これに対し、『新報』1918年(大正7年)8月25日号から9月25日号の四回に亘り社説で米穀専売法私案を提示する。米価を調節し、生産者にも消費者にも生活の安定をもたらすには、政府が米価の安いとこき買い上げ、高いときに売り出して、平準化する常平倉式では不十分であり、専売制が必要である。ただし、タバコのようにすべての米穀が対象というわけではなく、部分的に生産者に自由裁量も認めている。 この1918年8月は、すでに述べた通り、富山県の滑川で最初の米騒動が起きている。この動きは全国に広がり、寺内正毅内閣は総辞職に追いこまれ、9月末に原敬内閣が成立する。それに伴い、農商務大臣は仲小路廉から山本達雄に代わる。前者が暴利取締令を発動して、米価を下げようと強硬策をとっていたのに対し、後者はこの方針を転換すると表明する。これによりパニックは収まり、米騒動は沈静化する。しかし、米価は下がらず、米価問題は世論にとって最大の関心事である。 湛山は、この社説のうち、9月5日号に発表した『騒擾の政治的意義』において、米騒動の発端となった米価の高騰の原因について分析している。湛山はそれを業者の売り惜しみではなく、政府の失政と指摘する。これは農業だけに限ったわけではない。明治維新以来、政府は慢性的な貿易赤字に苦しみ続けてきたが、第一次世界大戦が勃発すると、交戦国は物資不足に陥り、これを外貨を獲得するチャンスと見る。政府は国債を発行して輸出為替資金を調達し、輸出を奨励する。米や小麦、豆類、雑穀、その他の食料品を始め、紙類、肥料、綿毛などの被服品を国内の需要を無視して、委細構わず輸出に回してしまう。この結果、物資の供給が大幅に不足し、その一方で、通貨流通量が急増し、日本経済は急激なインフレに突入する。米価の急騰は総合性を欠いた政府の経済・産業政策に起因しているのであって、米屋に圧力をかけたところで価格が下がるはずもない。 こうした状況の下で湛山は米穀専売私案を発表する。米騒動によって既存の米の生産・流通・販売のシステムがダメージを受けたが、それを回復させるよりも、統一的に管理できる専売制に変更すべきだと湛山は訴える。これには多くの賛同者が現われ。翌年、松崎伊三郎や鈴木梅四郎、白柳秀湖、石沢久五郎などが加わって米穀専売研究会が発足する。1920年(大正9年)夏、共同で7章44箇条に及ぶ「穀物専売法草案」をまとめ、鈴木の在任していた政府の財政経済調査会に提出している。しかし、原敬内閣はこの提案を斥け、常平倉方式を採用する。翌年4月、食糧管理特別会計法が公布される。これが後の食糧管理法の原型であり、最終的に廃止が施行されるのは2007年4月のことである。 湛山は、以後、政府の農業保護政策を厳しく批判し続ける。中でも、1922年6月の社説『農業政策の改革』で、米本位の政策は商工業の発展を阻害すると共に、小作争議の頻発を招き、農業の収益を減らしているため、改めるべきだと主張している。米だけでなく、果物や野菜、畜産といった農業の多角化を目指し、それを支援するための組織の改革をすべきだと農業の構造転換の必要性を訴えている。たんに米価の変動に対処療法的に対応するのではなく、農業全体の将来像に立脚した総合的な政策が必要だ。 湛山は、その後も社説などで農業問題に言及し、1927年7月25日、一連の農業に関する研究をまとめた『新農業政策の提言』を東洋経済新報社より刊行する。これは、初めて、湛山が発表した体系的な政策提言である。 湛山は、まず日本の貧困を分析し、その原因を当時一般的に信じられていた「天恵の不足」ではなく、「人工が足りぬ」と解き明かす。「天恵の不足」のために、農業の生産力が上がらない以上、地主と小作人の間での利益の分配が農業問題であるという消極的な考えを批判する。農業はまだまだ成長できる。国を豊かにするのは、資源を所有しているか否かではなく、それを活用できる知恵や技術があるかどうかである。湛山は、アダム・スミスの「土地気候領土の広さ、此等を一定の条件として、而して其条件の下に、国民の労力は其国の資源である」という見解に対し、「私は寧ろ此条件をも除いて、労力をば唯一無二の資源であると説きたい」と主張する。これが小日本主義に基づく産業政策の基本的発想である。貿易赤字を解消するには、国際競争力のある商工業を育成すべきであって、むやみやたらと農産物を輸出に回すべきではない。言うまでもなく、商工業発展のために、農業を縮小する必要はない。農業を近代化し、多角化を進めるべきである。それには、支援する組織を拡充し、新農業政策を実施しやすいように中央ならびに地方政府の行政改革も欠かせない。 湛山は自説を農業生産引き合い論に依拠して展開している。調査してみると、地主の土地賃貸収益が公債より利回りが高いだけでなく、平均年率10%以上の自然増もあり、「他の放資と比較して断じて利廻りの低きものにあらざる」。また、自作農にしろ、小作農にしろ、収益率は、投資資本から地価と家計費を除き、地価の自然増分を収入に入れると、「事実は相当高率」になる。これにより、湛山は、農業生産は不引き合いであるから、商工業成長のために農業縮小はやむなしという通念を斥ける。それはあまりにも農業に対して無気力である。決められた大きさのパイをいかに分け合うかではなく、パイをどのように大きくしていくかを創意工夫するべきである。 農業問題にとり組み始めた当初の湛山は、自由貿易と国際分業の観点から、商工業発展のためには、農業の縮小はやむを得ず、地主と小作人の間での適切な分配を考慮すればよいと考えている。しかし、考察を進める過程で、農業にも近代日本における積極的な意志を見出していく。1923年(大正12年)4月、湛山は山梨県で起きた小作争議を視察し、地主が小作人から搾取しているという素朴な階級闘争の図式が見当外れであることを実感する。小作人が貧困に喘いでいるのは確かであるとしても、地主も決して楽ではなく、農村経済全体の停滞が背景にある。農村の貧困を解決するには、農業を構造的に転換し、振興策を講じる必要がある。農業が衰退しているのは、自然の成り行きではなく、政府に総合的な産業政策が欠けているからである。 新農業政策論には、農業の近代化、農地の集約化、米作中心の放棄と農業の多角化、地域独自の創意工夫を生み出すための地方分権・行政改革、新たな農業の知識・技能を修得する教育制度の改革などが含まれている。湛山は、この変革によって農村は自活できると提言する。実は、こうした提言は湛山だけではない。宮沢賢治も農業の多角化・近代化や農民の意識改革を試みている。両者に接点はなく、まったく別個に試行錯誤して同じ結論にたどり着いている。米作中心と保護政策が日本農業の根本的な問題であり、その改善が農業再生には不可欠であるという見解は考慮されてしかるべきある。しかし、政府がそれを実際に生かすことはない。農業に関する流れは湛山や賢治の提案とは別の不穏な方向に進んでいく。 1930年(昭和5年)、先に述べたように、日本は昭和恐慌と呼ばれる深刻な経済危機に陥り、特に、農村は壊滅的な打撃を受ける。世界恐慌のため、主要輸出品目の生糸・繭価が暴落し、30年に豊作による米価下落、翌年は東北地方が大飢饉に見舞われ、欠食児童や少女の身売りなどの惨状続出、農村の困窮は危機的状況に追いこまれる。五・一五事件にも関与した権藤成卿や橘孝三郎らがこうした窮乏農村再建の理念・実践を提唱する。これは農本主義と呼ばれ、日本ファシズムの一つの源流である。1932年(昭和7年)、斉藤実内閣に対し、農村不況を背景に農村救済請願運動が全国的に展開される。長野朗らの農本主義団体・農民組合が国会に陳情を行っている。また、内務省・農林省が中心となって農村救済のため、自力更生・隣保共助を提唱し、産業組合を拡大させ、農民の結束を図る。さらに、国会も時局匡救費予算を可決し、農民を公共土木事業に就労させて、現金収入を得られるようにしている。しかし、農村の不満は収まらない。 1937年(昭和12年)、盧溝橋事件が勃発し、日本は中国との泥沼の戦争に入りこむ。日中戦争遂行のため、近衛文麿内閣は、挙国一致・尽忠報国・堅忍持久をスローガンに国家総動員運動を推進する。翌年、政府の農林水産業政策への協力を目的に、8団体が集まって農業報国連盟が結成される。1939年(昭和14年)4月、政府は米の集荷機構を一元化し、統制下に置くため、米穀配給統制法を公布する。しかし、生産低下による食糧危機が進行し、同年11月、強制的に買い上げる供出制を実施するが、深刻さがさらに増し、41年(昭和16年)4月には、配給通帳制を導入する。1939年9月18日、政府は、価格を据え置いて、値上げを禁止する公定価格制を実施し、同時に、賃金臨時措置令と地代家賃統制令も出され、これらは合わせて九・一八ストップ令と巷で揶揄される。けれども、物資不足から闇取引が横行し、闇価格が生じ、事実上価格の一元化は有名無実となる。そこで、政府は10月に価格等統制令を公布、さらに、12月、食糧増産・確保のため、地主の利益を制限する小作料統制令を実施している、1941年4月、生活関連物資の生産・販売を統制する生活必需物資統制令を公布したが、12月にそれは物資統制令に吸収され、配給・切符制が導入される。1942年(昭和17年)、政府が食糧の生産・流通・消費に亘って管理・統制する食糧管理制度が始まり、農業は完全に総力戦体制に組みこまれる。それは湛山が提起した米穀専売制などの農業のあり方とまったく似ても似つかぬものである。1944年(昭和19年)と45年(昭和20年)、米は例年の6割程度しか収穫できず、終戦後の深刻な食糧不足の一因となる。 |