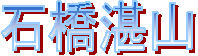Copy Right and Credit 佐藤清文著 石橋湛山
初出:独立系メディア E-wave Tokyo、2007年10月16日 本連載の著作者人格権及び著作権(財産権)は すべて執筆者である佐藤清文氏にあります。 リンク以外の無断転載、無断転用などをすべて禁止します。 |
|
第一節 金解禁論争 ジャーナリストとしての手腕はすでに業界内では知られていたものの、「石橋湛山」の名が広く認知されるようになったのは、1920年代に熱く論じられた金解禁論争である。 この頃から湛山は活動の幅を大きく広げている。1924年12月、石橋湛山は『東洋経済新報』の第5代主幹、次いで、翌25年1月に代表取締役専務に就任する。東洋経済新報社が社長制になるのは1941年からであるため、彼はわずか40歳で同社のトップに就いたことになる。当然、そのような地位にあれば、社外の人脈も広がる。ジャーナリストのみならず、政治家や学者、実業家とも交流を深めている。「石橋湛山」という名が政財界にも広く知られていくのはこの頃からである。社交は、彼にとって、人脈だけでなく、さまざまな知見を生み出すヒントにもなっている。実際、湛山自身も、「太平洋問題研究会」や「米国問題研究会」、「金融制度研究会」、「経済倶楽部」など社内外に多くの研究会を発足させている。中でも、経済倶楽部が、新報社が1931年に牛込から日本橋に社屋を移転したのを契機に経済知識の交流と研究を目的に設立され、全国29ヵ所に支部を置くほどの大規模な組織である。湛山も各支部で講演している。当時はマスメディアが未発達だったため、講演は重要な啓蒙活動であると同時に、中央と地方の人的・知的な結びつきを強めていく場でもある。 主幹に就任する二年前の1922年、湛山は、鎌倉町(現鎌倉市)に自宅を新築している。1889年に東京と軍港である横須賀を結ぶ目的から横須賀線が開通し、その経由地の鎌倉は東京の通勤圏として発達している。横須賀線は専軍的思考の下に強引に用地を買収して、敷設されたため、非常に効率的な運行が実現している。全線電化も1931年と格段に早い。芥川龍之介も横須賀の海軍機関学校で英語を教えていた時期に、東京の出版社との往来がいいこともあり、鎌倉に住んでいる。さらに、23年の関東大震災による東京の壊滅的状況を逃れて、多くの文学者が鎌倉に居を移し、彼らは「鎌倉武士」になぞらえ、「鎌倉文士」と呼ばれている。湛山にとって、鎌倉への転居は新たな経験の機会となっている。彼は、24年から28年に町議会議員を一期務め、初めて政治に直接携わっている。まら、横浜高等工業学校(現横浜国大)で24年から27年の間経済学担当講師として教鞭をとっている。 なお、この通勤車内も、湛山には、貴重な読書の時間である。「本を読むということは、いわゆる原書を読むことだと心得ておる。日本語の本を読むというのは、読書のなかに入れておらぬ」(『湛山座談』)。ただし、カール・マルクスの『資本論』は「英語で読みました。ドイツ語ではとてもついていけなかった」。 いわゆる金解禁論争がこの時期に沸き起こったわけだが、その前に金本位制と金輸出禁止に至る経緯に言及しておこう。 「金本位制(Gold Standard)」は、貨幣制度の基盤となる本位貨幣の単位を一定量の金と等価交換の関係にある法的に定めた制度である。それは金貨本位制と金核本位制に大別される。 金貨本位制は、金貨が実際に流通しているかどうかは別にして、金貨の鋳造・廃幣・輸出入のいずれの自由も認められる制度である。これは第一次世界大戦以前に国際的に採用され、狭義の金本位制と理解されている。 金核本位制は金地金本位制と金為替本位性の二種類に分けられる。前者は金貨を本位貨幣として鋳造せず、金兌換の請求に応じて金地金が用いられる。後者は自国通貨は金兌換されないけれども、金兌換できる他国通貨もしくは金為替と一定比率で交換可能な制度である。 金本位制が国際標準となったのは19世紀後半からである。産業革命に伴う商品生産の急増と国際貿易の規模拡大、欧米諸国の海外投資の増大により、各国の経済面での相互依存が進む。こうした事情を背景に、国際的な商取引や金融取引の決済を迅速化でき、外国為替相場が落ち着き、その上、国内通貨の安定を維持することが容易になるという理由から金本位制が各国の間に広まる。この均衡の自動調整作用のため、国際金本位制が確立していく。 単純な例を挙げよう。ある国の国際収支が赤字になると、為替相場が下落し、海外へ金が流出する。国内の通貨供給量がこれに応じて減少し、物価が下落するので、輸出競争力が高まる。すると、国際収支が好転し、物価の上昇が始まり、為替相場が安定する。どうしても維持できなくなった場合、国際ネットワークから一時抜け、体力を回復させた後に改めて復帰すればよい。 しかし、金本位制のメリットは、反面、経済を国内問題にとどめ、国際協調の動きにつながらない原因でもある。こうした経済に対するドメスティックな態度が全体主義の台頭を招いた一因として、第二次世界大戦後、経済は国際問題として考えられるようになっている。 1816年、イギリスが世界で最初に金本位制を採用したのを皮切りに、71年にドイツ、73年にアメリカと欧米諸国が相次いで導入する。日本は、1871年(明治4年)、新貨条例によって通貨単位を「円」とする金本位制を採用する。しかし、経済基盤がまだ脆弱で、慢性的な貿易赤字が続いたため、金貨の流出が相次ぎ、政府は金銀複本位制、さらに銀本位制へと変更している。完全に金本位制が確立するのは、日清政争以後のことである。 第一次世界大戦が始まると、各国共に金本位制を停止し、管理通貨制度へと移行する。この点からもこの大戦がかつてない総力戦であったことをよく物語っている。戦争に伴う金の国外流出を危惧し、1917年(大正6年)、アメリカが金への兌換の一時停止と輸出禁止に踏みきると、日本政府もこれに追随する。この大戦の結果、英国は債務国へと転落し、合衆国が世界最大の債権国へと変貌する。日本も、アジア方面の貿易を独占したおかげで莫大な貿易黒字を手にし、債務国から債権国へと成長し、新興工業国と世界から見られるようになっている。 大戦終結後、1919年6月、アメリカは金本位制を再開する。しかし、日本政府は本来戦時下での一時的措置であったはずの金の輸出を解禁しようとしない。立憲政友会政権は、積極財政政策と共に、北洋軍閥の北京政府への大量借款を用意するために、金の禁輸を続ける。1922年(大正11年)4月から5月にかけて開催されたジェノア会議において、各国が一刻も早く金本位制へ復帰することを求める決議が出されている。 しかし、金の禁輸政策は日本経済にダメージを与える。貿易収支は赤字に転落し、為替相場も下落している。金本位制の停止は固定相場制から変動相場制への移行を意味する。金本位制実施期において、日本の金平価は100円=49.816ドルに固定されていたが、1924年には100円=38ドルにまで下落している。第一次世界大戦中、欧米諸国の輸出が落ちこんだため、その特需により無数の成金が生まれ、日本は開国以来最大の繁栄を迎えたが、戦争終決に伴い、工業生産力が復活すると、急速に不況に陥ってしまう。国際競争力の想定的な下落により、日本は貿易収支の赤字に苦しむことになる。政財界は、金輸出を解禁し、日本経済を厳しい国際競争にさらさせて、企業の整理・合理化を断行、真の実力をつけさせるべきだと共通して考えている。 ただ、金解禁を旧平価でするか、新平価でするかで意見が割れている。当時の政府や財界人は円価格の低下を国辱と恥じ、旧平価での金本位制への復帰を悲願とする。何としても為替レートを引き上げるためには、輸出を増やすことが至上命題である。小林多喜二の『蟹工船』で扱われた北洋漁業の過酷な労働環境も金解禁問題と無縁ではない。蟹缶は貿易収支の改善に貢献できる品目の一つであり、その生産過程での労働環境がなおざりにされても、国家目標の達成のためにはこうした犠牲もやむを得ない。それを守るために、軍隊が動員されたとしても、不思議なことではない。 湛山らの『東洋経済新報』は旧平価金解禁を当初は主張していたが、1924年以降、平価切下げを行った上で金解禁を実施すべきという新平価解禁論を展開する。100円=40ドル近辺の為替相場が20ヶ月以上も続き、経済活動もこの水準を前提として行われている。現在の円為替の相場は国力低下ではなく、物価の国際比較の高騰の反映である。旧平価で解禁した場合、平均物価が約25%低下し、ようやく関東大震災の痛手から復興しつつある経済を冷え込ませる。むしろ、現状を踏まえて、新平価での金解禁を実施すべきである。この湛山の説に、エコノミストの高橋亀吉や『中外商業新報』の小汀利得、『時事新報』の山崎靖純らも賛同し、彼らは「新平価解禁四人組」と呼ばれるようになる。 ところが、政府は旧平価による金解禁の方針を崩さず、在外の政府保有の金の正貨を払い下げたり、金の現送を行ったりして円高を図っている。しかし、1927年、金融恐慌が発生する。多くの金融機関の破綻や企業倒産が起こり、政府はこの状況では時期尚早として金解禁を先送りする。 1929年7月、金解禁を公約の一つとして掲げた浜口雄幸民政党内閣が成立する。大蔵大臣には日銀総裁を二度務めた井上準之助が選任される。湛山は、組閣の二週間前に、火曜会の会合で、この初の明治生まれの総理と会った際、金解禁を慎重にするように提言している。ライオン宰相は経済問題に疎いことを辞任しており、その方面の「エキスパート」(『湛山座談』)に任せるから間違いないと応えている。それが井上準之助というわけだが、これは非常に皮肉な人選である。田中義一政友会内閣が29年5月に金解禁に踏み切りそうだという噂が流れ、証券市場が不安定化したときに、井上は、団琢磨日本経済連盟会長と郷誠之助同常務理事と共に、三上忠造蔵相に直談判してその動きを止めている。湛山はこの変節を井上の自信過剰さに見ている。どれだけ困難な問題であっても、自分ならできるというわけだ。 井上蔵相は、金解禁に備えるため、予算の削減、公務員給与の減額、在外正貨の補充、解禁に関する広報を行い始める。三井や三菱を始めとする財界の主流のみならず、アカデミズムやジャーナリズムからも歓迎されている。中でも、三井銀行の池田成彬は、金解禁に踏み切ったら、それを支援すると井上に約束している。 湛山ら新平価解禁四人組は、ジョン・メイナード・ケインズの『貨幣改革論』に基づいて、政府の方針を批判する。物価水準は安定させるべきであって、インフレのみならず、デフレも避けなければならない。そのために、現実の為替レートに見合う円の価値を切り下げた上で金解禁する必要がある。政府は消費節約を呼びかけ、緊縮財政をとるつもりだが、再生産を拡大するような合理的消費を刺激しなければ景気は回復しない。井上の後に蔵相に就任する高橋是清も企業の国際競争力を強化し、国際収支の均衡を回復するのを優先すべきであって、金解禁を急ぐことはないと政府の方針に反対している。彼は、1931年に、赤字公債を発行して、それを日銀に引き受けさせ、市中に売り出す政策を採用する。また、財界人の中にも、武藤山治鐘ヶ淵紡績社長や各務謙吉東京海上会長、宮島清次郎日清紡績社長、大川平三郎富士製紙社長らも賛同している。 加えて、嵐山は、『湛山座談』によると、井上蔵相に金解禁の噂が流れると、投機筋が思惑買いを始め、円買いドル売りが加速し、「当局者はもっと金解禁を緩めるつもりであっても、いやおうなしに持っていかれる。それが危険だ」と進言している。しかし、この忠告は無視され、円の急騰を背景に金解禁は前倒しされる。 浜口内閣は、29年11月、旧平価での金解禁を決め、翌年の1月11日、それを実施する。井上は、同年7月、投機筋の思惑買いを沈静化させるため、横浜正金銀行に対し、必要な場合に正貨の現送を認めることを条件として、顧客の請求に応じて無制限にドルを売って為替相場の維持を図る「為替統制売り」を命じている。しかし、為替レートを14%も切り上げたこの身の丈以上の金解禁は失敗に終わる。輸出の減少が予想されたため、政府はデフレ政策をとり、国内の需要を縮小させて輸入を減らし、経済収支の均衡を図り、経済は停滞していく。そこへ、1929年10月二四日の「暗黒の木曜日」に端を発する世界恐慌が追い討ちをかける。アメリカの消費は大幅に冷えこみ、さらに、世界の市場は縮小し、日本からの輸出は激減して、経済収支は悪化する。加えて、恐慌が起きて信用収縮が始まれば、金利が上昇するので、日本から資本が海外に逃げ出し、資本収支も悪くなり、金も流出していく。ウォール街で株が大暴落したにもかかわらず、日本政府が旧平価での金解禁に踏みきったのは、考えうるだけでおよそ最悪の判断である。30年1月から5月の間だけで、1億9600万円分の紙幣が金貨へと換えられ、正貨2億2000万円が流出している。さっさとしなければならなかったことを自分の都合で先送りしているうちに、タイミングを逃し、避けなければならない時期に実施に追いこまれるという最低のシナリオを政府は選んでいる。しかし、浜口内閣は総選挙が近づいていたため、この現状を公表せず、隠蔽し続ける。 政府がいかに情報を隠そうが、経済状況が転がり落ちているのは誰の眼にも明らかである。デフレがさらに進んで物価は下落し、輸出は激変して、企業倒産が相次ぎ、失業者が待ちに溢れ出す。1930年には、鐘ヶ淵紡績や東京市電、東洋モスリンなどで大規模な労働争議が勃発している。さらに被害を被ったのは農村である。輸出不振に伴い、生糸・繭価が暴落し、30年、豊作による米価下落、いわゆる豊作飢饉が起きたかと思ったら、翌31年には一転、東北地方が冷害に襲われ、大飢饉に陥ってしまう。 湛山は、こうした現状を鑑み、1930年5月から、金本位制を再び停止するか、もしくは通貨を切り下げることを提案し始め、9月以降、積極的に提言していく。 そんな中、30年11月、東京駅のホームで、浜口首相が右翼の青年に狙撃される。一命はとりとめたものの、彼は登院できず、療養生活に入る。事実上の総理不在という政治空白が生まれ、混乱する経済状況の収拾が滞ってしまう。 31年夏に恐慌がイギリスにも飛び火し、9月、英政府は金本位制の停止を発表する。このとき、池田成彬の指示で三井銀行が、為替統制売りを利用して横浜正金銀行を通じてドル買いに走っている。これは、日本も近いうちに金輸出が禁止になると読んだ思惑買いであり、金が大量に海外に流出していく。井上蔵相は、この事態に対し、公定歩合を引き上げ、金融の引き締めをとり、ドル買い用の資金を断つべく試みる。そのため、国内の不況は一段と厳しさを増す。31年4月、浜口内閣は総辞職し、代わって若槻礼次郎民生党内かが発足する。しかし、井上が留任したこの内閣は緊縮財政と行政整理を継続し、満州事変不拡大を約束したけれども、閣内不一致で12月に崩壊する。それを受けて、成立した犬養毅政友会内閣は、高橋是清蔵相が主導し、金輸出の禁止を決定する。この判断に踏みきったのは、実は、日本だけではない。日本同様、イギリスも31年、アメリカは33年、37年、フランスが最後にこの制度を停止する。この間、各国は平価の切り下げによる輸出促進政策を展開し、他国の金本位制離脱によってその効果が相殺されている。 金解禁論争において、湛山の見解はつねに適切だったのであり、それによって彼の名声は高まっている。しかし、その後の日本を「悲境に立たしめたのは、実に昭和五年の金解禁だった」と『湛山回想』の中で振り返っているように、この帰結は彼にとって苦々しいものでしかない。世界は大恐慌時代へ突入し、国際連盟に象徴される第一次世界大戦後に芽生えた国際協調の流れは停滞し、各国共に内向きなブロック経済の形成に傾斜する。日本でも五・一五事件を直接のきっかけとして政党政治が幕を閉じ、その代わりに、軍部が台頭し、軍国主義の時代を迎えている。右翼のテロが頻発し、暴力と恐怖、狂信が社会を覆い始める。32年2月に、井上準之助、翌3月に団琢磨がいずれも血盟団に暗殺される。小日本主義と正反対の大日本主義の方向へと社会が向かっていく。 けれども、湛山は投げ出したりはしない。金解禁論争は湛山の戦い方が顕著に現れている。ある課題に対して、根拠を示し、反対論を批判しつつ、自説を展開する。政治や社会が彼とは違う選択をした場合、「だから言わんこっちゃない」と不平をこぼしたり、無視したりせず、生じてくる弊害をいかに最小限にとどめるかを提言する。湛山は下がりながら戦っている。後退しながら戦い続けている。湛山は、こうした「後退戦」とも呼ぶべき戦い方で、小日本主義による数多くの政策論争を繰り広げる。
|