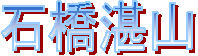第五節 政党政治の自殺
1928年2月、第16回衆議院議員選挙が実施される。これは念願の普選であると同時に、初の中選挙区制(単記)による選挙である。区割りは三人区が53、四人区38、五人区31という構成である。戦前、衆議院選挙の場合、たいていは農閑期である冬の平日が投票日に選ばれている。
普選により、日本でも代議政治が本格的に指導すると期待されたが、それは裏切られる。前述した自由主義や民主主義の系譜を踏まえたコミュニケーション論としての代議政治、すなわち討議民主主義の欠片もない見るも無残な状況である。普選後、政党は失態を繰り返し、世論の失望、官僚や軍部の暴走を招き、最後には自殺行為にまで至ってしまう。
1890年(明治23年)7月1日、日本初の国政選挙である第1回衆議院議員選挙が実施される。制限選挙であることはすでに述べたが、他にもいくつかの特徴がある。選挙制度は小選挙区制を採用し、その内訳は定数300に対して、一人区214、二人区43の構成である。
一人区は単記であるが、二人区は二名連記である。投票に際しては住所氏名を記入の上捺印する記名投票である。しかも、立候補届出制でなく、また投票を組織化する政党の下部組織も未発達だったため、政界進出の意思のない渋沢栄一が東京5区で危なく当選するところだったり、鈴木重遠や元田肇など複数の選挙区で当選した代議士も出現している。選挙結果は民党、すなわち野党が吏党、すなわち与党の倍の議席を獲得し、圧勝する。
少数与党のために政権運営がままならず、業を煮やした政府は、1892年、早くも二度目の総選挙にうって出る。同じ徹を踏むまいと政府は、2008年のジンバブエの大統領選挙さながらの露骨で野蛮な選挙干渉を行っている。特に、自由民権運動の中心地だった高知や佐賀は殺傷沙汰が相次ぎ無政府状態に射陥ってしまう。ところが、ここまで非道の限りを尽くしたにもかかわらず、選挙の結果はまたしても民党の圧勝に終わる。
したり顔で、日本人は昔からお上に弱いと語るメディア・タレントも少なくないが、翼賛選挙での斉藤隆夫の当選が示している通り、暴力的な強制には抵抗する傾向が歴史的には見られる。このような暴力を用いた選挙干渉に対し世論からの批難が高まり、松方正義内閣は総辞職に追いこまれる。以降、選挙を繰り返しても民党優位の議会構成に変化はなく、少数与党を前提として政府は政権運営を余儀なくされていく。
1900年(明治33年、第二次山県有朋内閣は選挙法を改正する。納税資格が10円に引き下げられ、被選挙権には納税金額の制限が撤廃されただけでなく、他にも大きな変更が二つある。それは秘密投票と大選挙区制である。特に、後者は強固に築き上げられてきた各議員の地盤を崩す効果があり、これにより、各府県の郡部では3から12、市部は原則1名を定員となっている。なお、京都や大阪など大都市は複数名、東京市は11名が定数とされている。
山県有朋にとって、政党や議会は反政府勢力以外の何物でもない。彼は地縁血縁に依拠して、陸軍や官界、宮中に人脈を構築し、前近代的な派閥を形成して政治的影響力を発揮している。彼は官僚主義者であり、大日本主義者であって、イマヌエル・カントやジェレミー・ベンサムとは相容れない。この大選挙区制はまさに彼の反政党政治の信念の表われである。従来の小選挙区制では二大政党になりやすい。事実、大日本帝国憲法の起草者の一人である伊藤博文は、政党政治への流れはとめられないとして立憲政友会を結成し、その初代総裁に就任している。立憲主義が何たるかを理解していない山県有朋は、伊藤とは逆に、その方向性をよしとせず、政党政治の進展を阻害すべく大選挙区制の導入を実現する。
その際、当時、すでに欧州で運用されていた比例代表制は、政党本位の政治が明確化するという理由で、論外とされている。19世紀にヨーロッパの各地で実施されていた比例代表制は、1900年にベルギーで初めて国政レベルで採用される。政党政治と同時に少数意見の尊重を促進しようとするのであれば、比例代表制がもっとも望ましい。事実、明治憲法と政党政治の整合性を解き明かした美濃部達吉も、拘束名簿方式の比例代表を提唱している。今日、世界的には、比例代表制が主流であり、中でも欧州においては圧倒的に優勢である。
政党政治に反対する政治家は、言うまでもなく、19世紀の欧米にも少なくない。合衆国第4代大統領ジェームズ・マディソンは政党を徒党と同一視し、否定している。大統領に選出される前、彼は連邦制を説く理論家であるが、この合衆国憲法の父によれば、政党は狭量かつ目先の利益に囚われ、数にものを言わせて横暴を働き、各政治家の自由な政治活動を妨げる害悪である。
しかし、山県有朋はそうした民主主義者とは異なっている。彼は憲法の立憲主義を無視して、天皇中心主義的側面をいかに運用するかを専心する。後の軍国主義は、軍人勅令や教育勅語、軍部大臣現役武官制など山県の推進した制度を根拠に成長し、暴走している。石橋湛山は、山県の訃報に際して、『東洋経済』1922年(大正11年)2月11日号で「死もまた社会奉仕」と書いているが、後の歴史は死さえも「社会奉仕」にならなかったことを物語っている。
山県有朋は愛国教育と軍備増強を柱とした天皇中心の国家建設に邁進する。しかし、1905年の段階で、すでに山県のヴィジョンが日本にとって危険であることが明らかとなる。愛国心は、外交問題、特に戦争の際に、政府に利用される。日露戦争遂行のために、政府は扇動した結果、民衆はポーツマス講和条約に納得できず、日比谷焼き打ち事件など各地で反政府暴動を起こしてしまう。愛国心は感情的であるため、一度燃え上がると、制御不能に陥る。愛国心を利用することは政治にとって自殺行為であり、愛国教育などもってのほかである。暴徒化した愛国者に恐れを覚えた政府は、現状に関する情報公開と合理的説明をする責任も果たさず、なおかつ自己批判もろくにしないまま、強権的な弾圧を始める。この時点で、政府は山県のヴィジョンを完全に否定しておかなかったために、禍根を残すことになる。
大選挙区制の下で、1902年の第7回から1917年の第13回までの総選挙が実施される。この選挙制度を改革するのが、藩閥に属さず、爵位を持たない原敬である。この平民宰相は前近代的な地縁血縁の縁故主義から脱却し、近代的な政治的人材のリクルート・システムの確立を試みる。そのために、政党を国家の統治を担う積極的・中心的な組織へと転換させようと腐心する。
湛山は、『湛山回想』において、明治以来の日本の政治を藩閥と政党の権力闘争の歴史であり、「議会ないし政党の勢力が伸張し、これに藩閥が降伏した」と陸軍省医務局長だった森鴎外に論じたら、「感服」されたと記している。原敬は藩閥を完全に降伏に追いこんだ凱旋将軍と言える。原は政党が選挙民を効果的に組織化する組織であることを見抜いている。これを実現するには、利益・要求を集約して、政策へと反映させたり、政治的人材をリクルートして政治的リーダーを育成・選出したり、政治的理念・主張を広報し、社会化するなどを政党の機能として実行していく。
原以前に、大隈重信が選挙運動の近代化を図っている。大正デモクラシーの時代が到来している。それにふさわしい選挙運動をしなければ、有権者にそっぽを向かれる。第二次大隈内閣の下で実施された第12回総選挙(1915年)には、現在にまで至る日本の選挙運動の原型が見られる。総理大臣の大隈が先頭に立って、選挙運動を指導し、各閣僚にも選挙区を積極的に回らせている。大隈は汽車に乗り、停車する度に、プラットホームで演説を行う、いわゆる「車窓演説」を全国規模で行っている。また、演説をレコードに吹きこみ、それを活用している。さらに、大隈は有権者に与党候補者への投票を依頼する電報を送っている。受けとった有権者の中には、感激のあまり、電報を額に入れて神棚に祀るものさえ現れている。ところが、この選挙で山県閥の大浦兼武内務大臣が大規模な選挙干渉をし、与党は勝利したものの、大隈内閣は総辞職に追いこまれている。
原敬内閣は、納税資格を3円に引き下げると共に、安定した政権運営を図るために、多数党が与党となるように小選挙区制の導入を骨子とした改正選挙法を可決させる。一人区295、二人区68、三人区11という構成で迎えた第14回総選挙(1920年)は、与党の政友会が過半数233を大きく上回る278議席を単独で獲得し、原の目論見通りとなる。
原は、小選挙区制を復活させたにもかかわらず、二大政党制による政権交代を前提とした政党政治を考えていたわけではない。55年体制化における自民党の一党優位制に近いシステムを狙っている。普通選挙実施にも、そのため、慎重な姿勢をとっている。けれども、コンセンサスではなく、多数決によって政権が形成される議会制と政党政治、すなわち代議政治を前提として国家の統治が運営されていく制度の基盤をつくったことは確かである。
政党間での政権の授受ではなく、選挙を通じて政権交代が初めて実現するのは、1924年に成立した加藤高明護憲三派内閣である。この「憲政常道論」に基づく政党政治は1932年の犬養毅政友会内閣まで続くこととなる。
普選が実施されるのに際し、選挙法とその関連法が改正・成立している。従来選挙活動の中心だった個別訪問は買収の温床として禁止される。選挙は冬に行われることが多いので、「寒いのにわざわざ遠くから尋ねてらっしゃって」云々となり、何がそこで繰り広げられるかは言わずもがなであろう。それを皮切りに、立候補届出制、供託金制、選挙資金の制限規定、選挙事務所の設置規制など細かな選挙規制がこのときから始まっている。また、植民地出身者も投票権を手にしている。ただし、台湾・朝鮮・樺太・千島は選挙区に区分されていなかったため、議席は与えられていない。1945年4月、台湾・朝鮮・樺太に議席が配分されたけれども、終戦を迎え、選挙が実施されていない。なお、在外邦人や皇族華族、現役軍人には選挙権が認められていない。
1928年に実施された初の普選は戸別訪問が禁止され、また有権者数の急増に伴い、大衆に向けた「文書戦と言論戦」の選挙運動を各陣営が実行する。政府も、これによって、選挙は公明正大で、政策中心の普選にふさわしいものとなると推奨している。言論戦とは演説を通じて選挙民へ訴える選挙活動であり、文書戦とは従従前の挨拶状や推薦状のみならず、党や候補者の政策・主張をパンフレット、ビラ、ポスターなどによってアピールする選挙運動である。中でも、ポスターは不特定多数の目に触れるため、最も重視され、政友会が風刺漫画家の北沢楽天を起用したように、芸術性の高い名作が生み出されている。ただ、ポスターが街の至るところを占拠し、ポスター公害とも言うべき状態に陥ってしまったため、以降は枚数や内容などに厳しい制限が加えられ、現在までポスターは印刷屋を喜ばせるだけの紙の無駄遣いと有権者から見られている。
確かに、政友会と民政党の二大政党の対抗意識はすさまじく、あらゆる面でしのぎを削っている。しかし、クリーンな選挙は期待された通りには実現しない。それどころか、以前にも増して、票の買収が相次いでいる。普選になれば、有権者数が激増するため、買収や贈収賄などの政治腐敗が減り、選挙資金もかからなくなると見られていたが、実態はその逆になる。新たに選挙権を手にした者たちの中から、自分たちもおいしい思いをしたいという不心得者が少なからず現れている。これでタダ飯やタダ酒にありつけるとか、選挙権をいい小遣い銭稼ぎが手に入ったとか、投票に行くために貴重な時間を費やすのだから、その分の手間賃をもらうのは当然だとかいったタカリが横行し、選挙資金はいくらあっても足りなくなってしまう。政治腐敗も普通化されたというわけだ。
選挙法による選挙資金は、有権者数を定数で割り、これに40銭をかけた額と決められ、その平均は1万2000円である。ところが、実際には、各陣営の間で「五当三落」とささやかれている。これは、5万円を使えば当選できるが、3万円に惜しんだら落選するという意味である。5万円は、現在の貨幣価値に換算すると、約7100万円に相当する。激戦区では、10万円以上も投じた候補者までいたとされている。公定選挙運動費内で抑えて、なおかつ当選するのは、極めて困難であるのが実情である。
また、単記式の中選挙区制も政策本位の代議政治の発達を阻害する。三人から五人の定数に対して一人だけに投票し、得票の多い順から当選が決まる。この中選挙区制の導入は、普選実施によって代議政治をより発展させていくという主旨とは矛盾している。今回は前回の選挙の4倍に有権者数が激増する。有権者数が増えれば、それだけその組織化が必要であり、政党の役割も重要となる。ところが、この制度は政党政治を嫌った山県有朋がその阻止を狙って施行した大選挙区制のヴァリエーションである。小選挙区制では多数意見、すなわち大政党が有利であるが、それと比べて、少数意見にも議席を得るチャンスがある。
政府はJ・S・ミルの言う少数意見の尊重ではなく、治安維持法の成立が示している通り、無産政党の躍進を恐れたからである。選挙マシーンが働かなくなる恐れがあるから、とにかく今のうちにゲリマンダリングしておこうというわけだ。少数意見を反映させるために、少数政党の議席に配慮するのであれば、比例代表制を中心とした選挙制度を導入すればよい。比例代表でも、方式によっては極端な多党化を招かない。中選挙区制は少数意見の尊重という点では中途半端である。中選挙区制への変更は既存政党が自分たちは少数代表だと認めたも同然である。しかも、選挙では、同じ党の立候補者同士で議席を争うことも多く、議会内で多数派工作が激化した場合、何かと火種となりやすい。
無産政党側も、普選になれば、自分たちが有利だと考えている。けれども、無産政党は労働農民党が2、日本労農党が2、社会民衆党が4の 8議席の獲得にとどまる。二大政党に埋没した結果に終わる。
社会民衆党から立候補して落選した菊池寛は、『敗戦記』において、新有権者が無産政党を支持してくれるはずだと思っていたと次のように振り返っている。
自分は最初から、相当自信があつた。普選に依る新有権者は七割五分あり、それがみな勤労無産階級である以上、勤労無産階級中心の政治を標榜する社会民衆党を支持しない筈はないと思つた。少なくとも、その一割位は、きっと社会民衆党に共鳴してくれるだらうと思つた。
政党政治時代に行われた以降の2回の総選挙も無産政党の議席は5で、むしろ、低迷している。もし小選挙区制のままで普選に臨んでいたら、無産政党は議席をもっととれなかっただろう。投票行動の研究は、今日の政治学において最も関心が高いと同時に困難なテーマでもある。選挙ポスターを見ると、二大政党はお互いを仮想敵として争点をつくり、それへの態度表明として自分たちへの投票を求めている。他方、無産政党は政党に対する帰属意識に訴えている。
代議政治において、現実にはともかく、投票行動は争点に対する態度で決定されるのが望ましいとされている。代表する者と代表される者の関係が固定化されているなら、選挙など無意味である。討議民主主義の観点に立てば、投票は政治的コミュニケーション過程の帰結であるから、熟議のために、争点を明確にするというのは政党やメディアは怠るべきではない。無産政党が躍進したのは、1936年に実施された第19回総選挙である。社会大衆等が18議席を獲得している。無産政党は、政党政治が崩壊した後に、既存政党への批判票の受け皿となっている。
8年間続いた政党政治の間、この第16回を含めて計三回の総選挙が実施されている。選挙結果はいずれも与党が勝利している。しかし、前述した通り、選挙結果によって政権が交代したケースは一度もない。現行の憲法と異なり、明治憲法下では選挙を政権選択の機能として認識されていない。首相は天皇によって選任されるが、それは元勲元老たちの推薦によるものである。選挙で議会の多数派になること自体が政権獲得には直結しない。首相には国会議員でなくても就任できたため、有権者の代表でもない人物が選ばれることも多い。ある内閣が行き詰った場合、総辞職をし、元老がその後継者を選ぶ。この頃は二大政党化しているので、次の首班は少数与党になるため、与党は政権運営を考えて解散総選挙に打って出る。前の政権が失敗した上での選挙であるから、現政権が有利であり、多数を獲得する。解散総選挙の結果、政権が選択されるのではない。政権が交代した後に、その正当性を得るために、解散総選挙が実施されている。
しかし、無産政党の伸び悩みは、政党政治にとっては不幸なことである。議会の勢力地図が普選以前と本質的に変わらなかったからである。政友会と民政党はその政策論争を忘れさせるほど「どろ合戦」(石橋湛山『湛山回想』)に終始している。二大政党は政権の維持や奪取のため、露骨な党派人事、党利党略に基づく政策、利権の獲得と身贔屓な分配、選挙における干渉や買収、軍や枢密院と連携を強化しての倒閣運動、スキャンダルの暴露などを繰り広げ、政党政治への一般世論のイメージは地に落ちていく。政権交代が起きる度に行われた党派人事は非常に広範囲に及んでいる。中央で政権が交代すると、野党系と見なされた地方の行政官たちは更迭され、その後釜に与党系の人物が抜擢される。当時の知事は公選ではなかったため、その座も選挙の結果次第であり、県庁を与党系の選対本部にする輩まで出現している。党派対立が激しい地域に至っては、警察署長や小学校の校長までも挿げ替えられることさえ見られている。加えて、巨額の利権が絡むインフラ整備や公共事業も選挙の結果が左右するため、癒着や腐敗が横行する。
明治憲法を含めて、当時の制度では代議政治を遂行するのは困難であったことは確かである。しかし、憲政常道論を推し進め、もう少しましにできたのではいのかと思われても仕方がないだろう。湛山は原理的な主張をしながら、一方で、現時点で行うべき最適な措置を提言している。政党はそうした工夫をせず、目先の利益にのみとらわれてしまい、代議政治の諸問題とまで言えないような愚行を続けている。
こうした政党政治に不満を募らせていったのが官僚と軍部、右翼である。政党の党派人事に振り回される官僚は「浮き草家業」と自嘲しながら、政党政治への憎悪を蓄積する。世論の政党政治不信を利用し、その弊害の「革新」を標榜する官僚は「革新官僚」と世間から耳目を集めるようになる。また、軍部は、政党政治下での外交方針であるワシントン体制の堅持や慢性的な財政の悪化により、度重なる軍縮が要求され、怒りは爆発寸前にまで達している。クーデターが何度となく計画され、未遂で終わったが、1930年9月、政党政治とワシントン体制への軍部からの決定的反撃である満州事変が勃発する。さらに、右翼は政財界の要人に対するテロを繰り返し、世の中を殺伐とさせていく。
1930年11月14日、浜口雄幸首相が東京駅のホームで右翼のテロリストから銃撃される。同年12月、元老西園寺公望の推挙により犬養毅内閣が成立したが、政党政治は風前の灯である。1932年1月に上海事変が起こり、2月、国際連盟の派遣したにリットン調査団が満州入りし、3月には満州国の建国が宣言される。同年5月15日、「話せばわかる」と制する1855年生まれの老首相を「問答無用」と若い海軍将校のテロリストが射殺する。この交わされた言葉は政党政治の終わりと軍国主義の始まりを告げるものとなる。
しかし、新聞や雑誌はテロリストの方に同情的に報じる。彼らの主張を垂れ流し、彼らは国難を憂い、義憤にかられて、行動した英雄だと言わんばかりである。そんな中で、石橋湛山は、『東洋経済』1932年5月21日号「社説」において、「顧みて我国は、本誌創刊以来三十有八年の間に、幾たびか難局に面して来た。しかし思うに、今日に越したる甚だしき危険に際したことはない……。累卵の危に際すとは、真に今日であろう」と書いている。
1935年2月、帝国議会で天皇機関説が突如として問題視される。野党政友会は岡田啓介内閣打倒のため、そのイデオロギーを追求し、それに対抗して、岡田首相も議場で機関説反対を表明する。しかし、天皇機関説こそ政党政治を明治憲法下でその正当性を保証する理論であり、それを政党が自ら糾弾するのは自殺行為にほかならない。国家の統治は完全に軍部と官僚の手に移る。
代議政治はこのようにして死を迎え、山県有朋の亡霊が日本を覆うことになる。
しかし日本の普通選挙は、あまりにもおくれて行われた。大正十四年にその法律が議会を通った時には、最早これに対してわれわれは感激を失っていた。何だ、今ごろになってようやく男子普選かと、いささか鼻であしらう気分であった。せめて大正八、九年ごろ、諸政党が尾崎さんと同様に、時勢の変化を早く察し、普選実行の決意をいだいたら、日本の民主主義はその時代にもっと固まり、したがって昭和六年以後軍閥官僚が再びその勢力を盛り返すがごとき不幸を防ぎえたかもしれない。
(石橋湛山『湛山回想』)
参考文献
天川晃他、『日本政治史─20世紀の日本政治』、放送大学教育振興会、2003年
天川晃他、『日本政治外交史』、放送大学教育振興会、2007年
石橋湛山、『石橋湛山評論集』、岩波文庫、1984年
石橋湛山、『湛山回想』、岩波文庫、1985年
石橋湛山、『湛山座談』、岩波同時代ライブラリー、1994年
岩崎武雄編、『世界の名著44』、中公バックス、1978年
岡義武、『山県有朋』、岩波新書、1958年
岡義武、『近代日本の政治家』、岩網現代文庫、2001年
柄谷行人、『ヒューモアとしての唯物論』、筑摩書房、1993年
柄谷行人、『日本精神分析』、講談社学術文庫、2007年
姜克實、『石橋湛山』、丸善ライブラリー、1994年
小林良彰他、『新訂政治学入門』、放送大学教育振興会、2007年
城塚登、『ヘーゲル』、講談社学術文庫、1997年
玉井清他、『歴史に好奇心 いつなぜ日本の選挙制度/日本コレクション奇譚』、日本放送出版協会、2008年
藤原帰一、『国際政治』、放送大学教育振興会、2007年
増田弘、『石橋湛山 リベラリストの真髄』、中公新書、1995年
増田弘、『石橋湛山研究 「小日本主義者」の国際認識』、東洋経済新報社、1990年
J・J・ルソー、『社会契約論』、桑原赳夫他訳、岩波文庫、1954年
|