特集:BRICS+
BRICSの台頭を描く:
宣言、構想、そして未来の展開
リオでの第17回BRICS首脳会議で、BRICSの機関車は静かに、
しかし紛れもなく、世界の力の変化する輪郭の中を動き続けている
Mapping the Rise of BRICS: Declarations, Designs and a Future Unfolding. With the seventeenth BRICS summit in Rio de Janeiro, the BRIC locomotive
continues to move, quietly yet unmistakably, through the shifting contours
of global power
Info-BRIICS War on UKRAINE #8067 4 August 2025
英語翻訳:青山貞一(東京都市大学名誉教授)
独立系メデア E-wave Tokyo 2025年8月7日(JST)
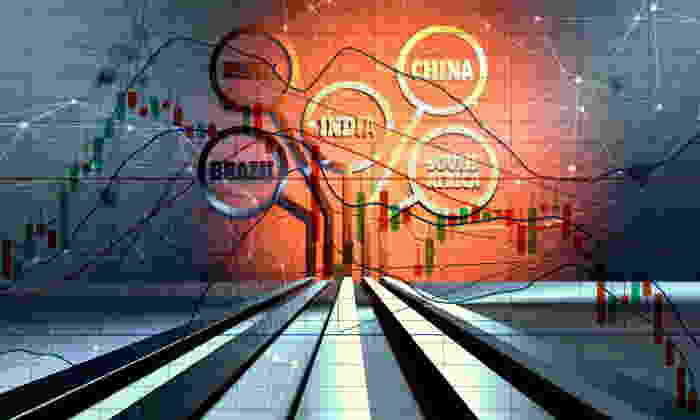
EMIR Research の創設者
2025年8月5日火曜日
筆者:ライス・フシン博士は、厳密な調査に基づく戦略的な政策提言に重点を置くシンクタンク、EMIR Research の創設者
本文
リオデジャネイロで開催された第17回BRICS首脳会議を経て、BRICSの機関車は静かに、しかし紛れもなく、世界の力関係の変遷の中で動き続けている。拡大、通貨の代替、制度改革といった表向きの議論の裏には、より深い連続性がある。それは、グローバル・サウスが、首脳会議を重ねるごとに、覇権国家を脱した秩序を築こうと、意図的かつ協調性を増す努力を重ねていることだ。
2009年から2025年までのBRICS諸国の宣言を体系的に検証すると、分裂ではなく、テーマの一貫性と着実な制度的成長が明らかになる。BRICS諸国は、反応的な発言者から建設的な設計者へと移行した。
しかし、批判は依然として続いている。BRICSを単なるおしゃべり集団、つまり宣言ばかりで実行力に欠ける集団だと見なす人もいる。しかし、もはやそのような見方は通用しない。宣言を精読すると、技術的な連携、政策の継続性、そして正式な体制の強化が見られる。かつては曖昧さの証拠として挙げられていた文書こそが、今やガバナンス・エコシステムの成熟を証明しているのだ。
17年以上にわたり、いくつかの中核テーマは不変のままである(図1)。グローバルガバナンス、特に国連安全保障理事会とブレトンウッズ体制の改革を求める声が強まった。また、国際法に基づく主権、不干渉、多国間主義の主張も強まった。BRICSは、一方的な強制措置、外国の介入、法の域外適用に一貫して反対し、平和的な紛争解決と主権平等を重視してきた。
平和と安全保障に関する協力も成熟してきた。テロリズムに対する言葉だけの非難から始まったものが、今では作業部会、行動計画、そして技術協力プラットフォームによって支えられている。BRICS諸国の宣言は、パレスチナ、シリア、スーダン、ウクライナといった地域紛争への対応を、連帯の意思を示すだけでなく、国際法と人道原則の規範的な声として、ますます重視している。
アフリカ、ラテンアメリカ、そして後発開発途上国への支援は、象徴的なものから構造化された枠組みへと移行した。BRICSパートナーカントリーの地位の導入と「アフリカの問題にはアフリカの解決策を」というスローガンは、支援がアドボカシーから構造的なものへと移行していることを示している。
金融分野において、BRICS諸国によるドル優位への批判は、姿勢から実践へと移行した。新開発銀行(NDB)と緊急準備金取極は、その初期のステップであった。直近では、BRICS諸国の宣言において、NDB内にBRICS多国間保証(BMG)メカニズムを創設すること、およびクロスボーダー決済の相互運用性に関する技術的進歩が提案された。これらの動きはまだ具体化されていないものの、EMIRリサーチが「BRICSの通貨ジレンマ:ドルを超えるための必要な質の高い飛躍」(2024年)で提唱しているように、外貨への依存とインフレ的な信用創造の両方を回避する、分散型で自己均衡型の貿易システムである相互信用決済(MCC)の論理をますます反映している。
近年、BRICSのアイデンティティはプラットフォームからプロトタイプへと決定的な転換を遂げている。2021年以降、テクノロジーガバナンスとAIが中心的な位置を占めるようになった。このブロックは、デジタルアクセスへの対応からデジタル主権の主張へと軸足を移し、AIガバナンス、サイバー規範、そして主権デジタルインフラに関する新たな枠組みを構築している。
BRICSは制度面でも密度を高めている。もはや単なる首脳会議の場ではなく、同圏の運営エコシステムは常設の作業部会、銀行間プラットフォーム、シンクタンクネットワーク、市民社会フォーラムなどから構成されています。宣言では、分野横断的な調整、2030年戦略、詳細な技術的付属文書といった、真のガバナンス能力を示す特徴への言及がますます増えている。
もう一つの変化は、BRICS諸国が人道外交と法的説明責任において果たす役割の拡大です。2020年以降、宣言では人道法、援助へのアクセスの円滑化、そして国際司法裁判所への明確な言及がより重視されるようになった。BRICS諸国は、長らく西側諸国の法的枠組みによって独占されてきたシステムにおいて、規範的なカウンターウェイトとしての立場を確立しようとしている。
この制度的成熟は、BRICS諸国の言語の進化にも反映されている。初期のBRICS(2009~2014年)は、発言力、代表性、多極性といった観点から発言していた。近年の宣言では、機敏性、公平性、説明責任、包摂性といった、より主張的な表現が用いられている。この変化は、BRICSが単なる構造的なカウンターウェイトではなく、価値観に基づく代替案を提示しようとする意欲を示している。
重要なのは、BRICSサミット2025が地政学的な突破口となることである。インドネシアが正式加盟国として承認され、マレーシアを含む11カ国がパートナーとして承認されたことで、BRICSは分散型かつ同心円状の拡大モデルを運用し始めている。このモデルは、合意を維持しながら、リーチを拡大する。
経済用語さえも変化している。西側諸国の貿易非対称性に対する批判は依然として残るものの、今では技術的なニュアンスを帯びている。官民連携による為替リスク軽減、インフラ情報ハブ、ESG(環境・社会・ガバナンス)に配慮した投資プラットフォーム、デジタルグリーンファイナンスの統合などだ。「BRICSへのエクスポージャー」は今や投資戦略の語彙に加わりつつある。政治的なシグナルではなく、信頼性の高い分散投資戦略として。
マレーシアの瞬間:観察者から指揮者へ
マレーシアがASEAN議長国となったことで、BRICS+の深化と多様化は戦略的な機会をもたらす。それは、どちらか一方を選ぶのではなく、グローバルな競争の場を形成することに貢献することだ。外交における実利主義、多国間の信頼性、そして進化するMADANI(国際秩序と地域秩序)枠組みで長年知られるマレーシアは、この再調整の時代において、橋渡し役と設計者という両面で貢献できる独自の立場にある。
マレーシアは、すでにBRICSパートナー国として認められており、金融イノベーション、テクノロジーガバナンス、開発協力という3つの領域にわたって戦略的連携を追求できる可能性がある。
BRICS諸国の宣言は相互信用決済(MCC)をまだ明示的に採用していないものの、その背後にある論理は形になりつつある。このシステムでは、他国にとって価値が認められる財・サービスを生産する国だけが持続的に信用を発行できる。ハラール製品やパーム油から半導体やグリーン部品に至るまで、世界的に需要の高い輸出品を持つマレーシアは、この基準を満たしている。安定した貿易黒字、多様な生産基盤、そして安定した通貨ガバナンスは、将来のBRICS+MCCのような枠組みにおいて、マレーシアを単なる参加者ではなく、安定と信頼の結節点として位置づける。
この信頼と生産の連携は、現在NDB内で構想中の多国間保証(BMG)メカニズムに直接結びついています。インフラ整備や持続可能な開発プロジェクトのリスク軽減を目的として設計されたBMGは、欧米のリスク評価や信用機関への依存を軽減する。マレーシアは、制度的な信頼性と投資適格水準のガバナンスにより、受益国としてだけでなく、地域のアンカーとしても優位な立場にあります。MCCのようなロジックと組み合わせることで、BMGは方程式のもう一方の側面、すなわち、生産的な意図が投資可能な成果に繋がることを保証する集団的信頼メカニズムを提供する。
マレーシアの戦略的価値は、さらに拡大している。デジタルおよび金融分野では、AIガバナンス、データフロー標準、サイバーセキュリティに関するASEAN-BRICS+フォーラムの開催が期待される。開発分野では、イスラム金融、ハラール規制の収束、生物多様性枠組みの整備を主導し、新興グローバル・サウスのアーキテクチャに価値に基づく規範を組み込むことができる。インドネシアなどの近隣諸国がBRICS正式加盟国となったことで、規制の整合性とイノベーション外交の可能性はかつてないほど高まっている。
BRICSの物語はもはやブロック形成ではなく、枠組みの進化をめぐるものです。問題は、世界が多極化しているかどうかではない。マレーシアのような新興アクターが、新たな構造に適応するだけでなく、それを形作るために前進するかどうかである。
この精神に基づき、マレーシアの進むべき道は、協調か対立かではなく、共創にある。
ASEANの声をBRICS+の中核に取り込み、相互信用を貿易の論理に組み込み、包摂的なガバナンスを現実的な多国間主義と整合させていくことです。今がその時ですが、その窓は狭いです。これは単に歴史を観察する機会ではありません。マレーシアの次の章を設計するための招待状なのです。
ライス・フシン博士は、厳密な調査に基づく戦略的な政策提言に重点を置くシンクタンク、EMIR Research の創設者です。
本稿終了
|
|
|